亜鉛は人体にとって欠かせないミネラルの1つですが、なかなか自分で補うことができないもの。
最近「亜鉛不足になりやすい」という認知度も上がってきており、「サプリメントで普段からとっている」という方も増えています。
しかし、そのように亜鉛をサプリで補っている方で、実際採血で亜鉛値を計測したら「亜鉛過剰症」になってきている方も。亜鉛不足も問題ですが、亜鉛のとりすぎである「亜鉛過剰症」でもさまざまな症状や副作用が出ることがあるのです。
今回は、亜鉛のとりすぎである「亜鉛過剰症」について、症状や副作用・亜鉛過剰症に関連した「銅欠乏」に至るまで解説していきます。
亜鉛不足については、ぜひ亜鉛不足の原因や症状・摂取量の目安について【食べ物や治療薬も】を参照してください。
Table of Contents
亜鉛のとりすぎ「亜鉛過剰症」による症状や副作用は?

亜鉛は本来体の成長や維持になくてはならない見寝られるです。2020年の厚生労働省による日本人の食事摂取基準では男性11mg/女性8mgが推奨量として規定されています。
しかし、サプリメントや強化食品などで推奨量を大きく超える亜鉛を長期間摂取すると、体内の亜鉛・銅・鉄のバランスが崩れ、種々の症状が現れます。
例えば、亜鉛の取りすぎによる症状として以下のものがあげられます。
- 消化器症状:高用量の亜鉛は小腸粘膜を刺激し、「吐き気・嘔吐・腹痛・下痢・食欲不振」といった消化器症状を引き起こします。急性中毒例では、摂取後数時間以内に激しい腹痛や嘔吐を伴うことがあります。
- 神経・全身症状:亜鉛のダラダラ摂りすぎると、全身の酸化ストレスを高め、神経にも影響を及ぼします。そのため、頭痛、発熱、倦怠感、末梢神経障害(しびれ・しびれ感)などの症状が出てくることもあります。
- 貧血症状:亜鉛不足による貧血も知られていますが、亜鉛の取りすぎでも貧血になることが、過剰な亜鉛摂取が小腸での銅・鉄の吸収を阻害し、ヘモグロビン合成に必須のミネラルが不足してしまうのです。
- HDLコレステロール(善玉コレステロールの低下):亜鉛過剰者では善玉(HDL)コレステロールが減少がしてしまうことがあります。そこから動脈硬化になるリスクも高くなります。
- 前立腺がんリスクの上昇:1日あたり100mgを超える亜鉛摂取をされている男性は、進行性前立腺がんのリスクが2.29倍(1.06~4.95倍)に上昇するという報告もあります。10年以上サプリメントで亜鉛を服用されている方の前立腺がんの発生リスクは2倍(1.42~3.95倍)に及ぶので、長期間内服されている方は注意が必要ですね。
このように、体にいいと思っていた亜鉛により様々な症状や弊害が引き起こされるということもあるのです。なんでも「摂りすぎはよくない」「バランスが大切」ということですね。
(参照:Zinc supplement use and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst. 2003 Jul 2;95(13):1004-7.)
(参照:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版))
(参照:厚生労働省 eJIM「亜鉛」)
(参照:Ingestion of Excess Zinc Augments the Osmotic Fragility of Red Blood Cells via An Increase in Oxidative Stress)
亜鉛過剰症の背景にある「銅欠乏」

長期にわたって亜鉛を過剰摂取することで、最も大きい理由が「銅欠乏」です。
実は、亜鉛と銅は小腸上部(胃・十二指腸・空腸近位部)で吸収される際、同じ吸収するタンパク質を介して、体内で吸収されます。
そのため、過剰に亜鉛をとると、吸収するためのタンパク質を亜鉛だけで使い果たしてしまい、銅が吸収できなくなってしまうのです。また、亜鉛過剰により誘導されるメタロチオネインという成分はは、銅に対する親和性が高く、腸管内で銅を捕まえて体内への移行を防ぎます。結果、血清銅・セルロプラスミン濃度が低下して全身の様々な症状が出てくるというわけなのです。
では、銅が少なくなるとどんな症状が出てくるのか。亜鉛過剰症ともオーバーラップしますが、以下の症状が言われています。
- 疲労・貧血・白血球数の減少:好中球減少や血球全体の低下も低下することが言われています。
- 骨粗しょう症・神経の損傷:銅が不足すると、コラーゲンがきちんと作られにくくなり、骨粗鬆症や皮膚・血管壁の脆弱化を招きます。
- 筋力低下や歩行異常:実際、亜鉛過剰症により銅欠乏をきたした症例報告によると、ビタミンB₁₂欠乏に類似したマヒしたような歩行・重度の深部感覚障害を呈して歩けなくなるという症状がでました。。
こうしてみると、貧血や神経症状などが中心ですね。
亜鉛は、実はサプリメントだけでなく、亜鉛が添加されている食事・亜鉛を使用している義歯・「プロマック®」などの亜鉛が含まれている処方薬など、食事以外の様々な経路で過剰摂取することがあります。
1つ1つは許容範囲内でも、知らずに1日耐用上限(35~40㎎)まで超過する例も少なくないのです。
そのため、当院では亜鉛不足で継続的に投与されている方は「銅」も一緒に測定し、銅欠乏に至っていないかチェックしながら慎重に投薬しています。
(参照:偏食による亜鉛過剰摂取が原因と考えられた銅欠乏性ミエロパチーの 1 例. 臨床神経 2016;56:690-693)
(参照:Ingestion of Excess Zinc Augments the Osmotic Fragility of Red Blood Cells via An Increase in Oxidative Stress)
亜鉛過剰症のリスクが高い方は?
亜鉛は、通常の食事ではむしろ不足しやすいことが多く、亜鉛過剰症には至りません。亜鉛過剰症のリスクが高い方は例えば次のような方です。
- 亜鉛のサプリメントを継続的に飲まれている方
- 亜鉛が含まれている義歯を使用されている方
- ミネラルが添加されている食事を非常によく摂られている方
- 亜鉛が含まれている薬(プロマック®)などを継続的に飲まれている方
などです。これらに該当されている方は一度「亜鉛値」の計測をしてみるとよいでしょう。
亜鉛の安全な上限値は?
亜鉛の安全な上限値は、厚生労働省によると下記の通りです。もちろん医学的な理由で亜鉛を処方され摂取している場合は該当しません。
| ライフステージ | 亜鉛の安全な上限値 |
| 生後6か月 | 4 mg |
| 幼児7-12か月 | 5 mg |
| 小児1-3歳 | 7 mg |
| 小児4-8歳 | 12 mg |
| 小児9-13歳 | 23 mg |
| 14-18歳 | 34 mg |
| 成人 | 40 mg |
ただし実際に診療をしていると「サプリメントで安全域で飲んでいたのにも関わらず『亜鉛過剰症』や『銅欠乏』になっていた」ということもよくあります。
そのため、亜鉛を継続的に飲まれている場合は定期的に医療機関に亜鉛を測定してもらうようにしましょう。
(参照:厚生労働省 eJIM「亜鉛」)
銅が多く含まれる食事は?

では、亜鉛過剰症で銅が不足していたとして、どのような食事に銅が多く含まれているのでしょうか。一般的には魚介類・肉類・豆類に多く含まれています。
例えば、100gあたりの銅が含まれる食材として、以下があげられます。
- 干しえび:5.17 mg
- ピュアココア(粉末):3.80 mg
- 蛍いか(生):3.42 mg
- ごま(いり):1.68 mg
- かぼちゃの種(いり・味付け):1.26 mg
- アーモンド(いり・無塩):1.19 mg
- 牡蠣(養殖・生):1.04 mg
- 豚レバー(生):0.99 mg
- 小麦胚芽:0.89 mg
- 乾しいたけ:0.60 mg
これらを中心に、1食分(例えば牛レバー50 g、焼き牡蠣3個約60 gなど)を組み合わせることで、効率的に銅を補給できます。
(参照:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年)
亜鉛のとりすぎ「亜鉛過剰症」に関するまとめ
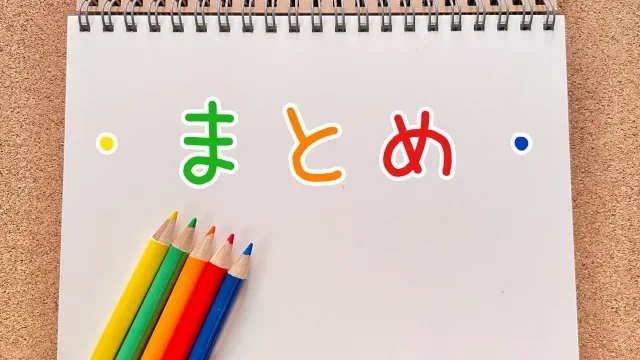
いかがでしたか?亜鉛過剰症の症状からリスクの高い方、亜鉛過剰症に欠かせない「銅欠乏」についてお話していきました。簡単にまとめると
- 亜鉛過剰症になると、頭痛・吐き気・下痢・食欲不振・神経障害・貧血・HDLコレステロール低下などの症状が出現することがあります。
- また、亜鉛のとりすぎにより前立腺がんの発生リスクも上昇します。(約2倍)
- 亜鉛をとりすぎると、「銅欠乏」になることがあり、血液検査異常や神経症状を中心とした症状が出ることがあります。
- そのため、適切にモニタリングしながらの補充が大切です。
といえます。当院でも亜鉛不足や亜鉛過剰症に対して、個別に相談をしておりますので、ぜひ気軽に来院・相談してください。
あわせてこちらもオススメです
- 【こむら返り】足がつる原因と治し方・予防について解説【漢方薬も】
- 亜鉛不足による「爪の5つの症状」について【白い斑点・横線など】
- 亜鉛不足の原因や症状・摂取量の目安について【食べ物や治療薬も】
- チョコレートの健康効果は?チョコレートと血圧やダイエット・ストレスとの関係について
- 鉄分不足による貧血「鉄欠乏性貧血」の原因や食事・治療について
【この記事を書いた人】
一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。


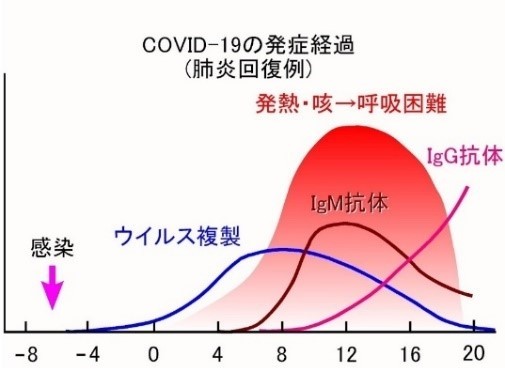

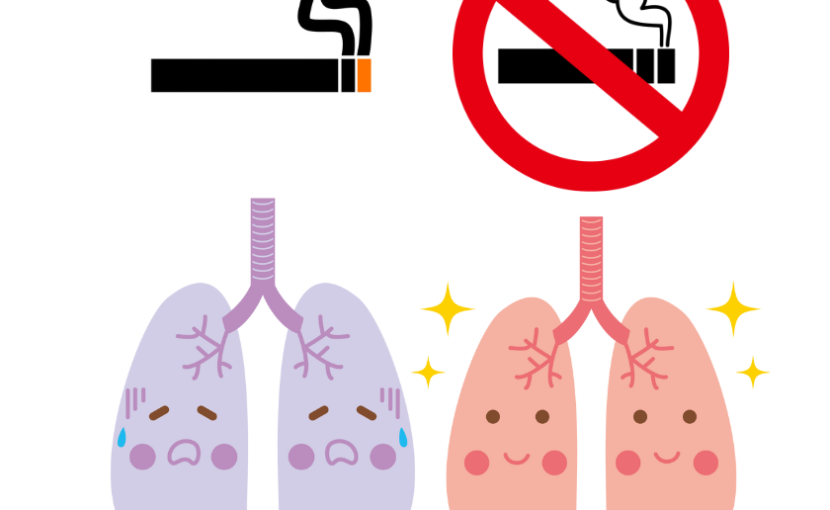

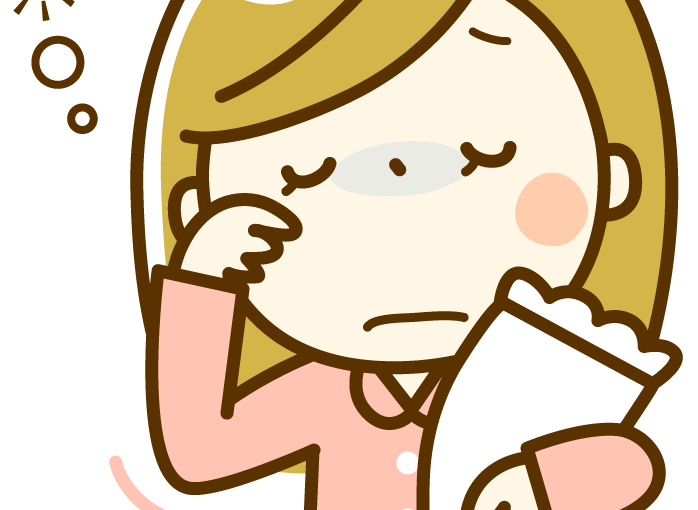









亜鉛サプリメントをあす〜服用する予定なの。副作用って、だいたいどんな症状があらわれそうでしょうか?
川愛様
コメントありがとうございます。亜鉛サプリメントを飲んですぐに、亜鉛過剰症になるわけではありません。
サプリメントの注意事項に「起こりうる副作用」が書いてあると思いますので、ぜひ確認してみてください。
持病をお持ちの方でしたら、一度かかりつけの医師に相談してみていただき、亜鉛をチェックしていただくとよいでしょう。
以上、よろしくお願いいたします。
とても参考になりました。
実は1ヶ月ほど亜鉛を高容量摂っていたところ髪の毛が抜け落ちるようになり中止しました。
中止して10日ほど経過しても変わらず抜け落ちるので亜鉛を過剰にとっていたための「銅欠乏」かなと思い「銅」を2〜4mgほどサプリで摂り始め1週間ほど経ちますが全くといっていいほど改善せず、シャンプーだけでなく何もしてなくてもするすると抜け落ちてきてる状況で悩んでいます。
もう少し銅が必要なのでしょうか?(銅も過剰症があるというので不安です)
田舎に住んでいるので病院も遠くていけません。
おの様
コメントありがとうございます。
非常に悩ましく、お辛い状況であること、伝わります。
拝見していないので、「診断をつける」ことはできませんが、
脱毛症にもいろいろあります。
亜鉛や栄養不足でないタイプもかなりあります。汎発性円形脱毛などでは、入院して治療することもあります。
遠いのもわかるのですが、一度皮膚科できちんと診ていただいてから方向性を見つけた方がよさそうです。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
いま、とても辛い状況にあったので少し心が楽になりました。
言われてみると年度始めで色々と環境が変化しストレスも大きかったりもしました。偶然亜鉛の高容量を摂り始めた時期でもありましたので、早合点で亜鉛だと決めつけてしまっていたのかもしれません。
週末に皮膚科を受診してみようと思います。
お忙しいところご丁寧に本当にありがとうございました。
コメント失礼致します。
亜鉛が必要とのことでサプリを1ヶ月以上服用しておりました。成人10mgが理想とのことですが、
間違えて50mgを2日に1回服用していたことに
今気づきました。
おととい、飲酒とチョコレートをとったので
気づかず1日1錠のんでいて昨日から吐き気が止まりません。対処方あれば教えて頂きたいです。
そのうち落ち着くものでしょうか?
きぬ様
飲酒もチョコレートも吐き気を誘発するので、飲み合わせは悪いですかね。
おちつくことが多いですが、続くようなら、素直に消化器内科に受診しましょう。
その際、亜鉛の血中濃度も調べてもらうとよいですね。
こんにちは。
風邪を年に3〜4回もひくので、免疫力を高めるため亜鉛サプリを摂取しようかと思っていますが、摂取量上限の40ミリが免疫力を高めるには必要とYouTubeなどでは盛んに言っていますが、その量を摂取しても大丈夫なのでしょうか?
何としても免疫力を上げて風邪を引かないようにしたいという切実な思いがあるのですが………。
青木様
コメントありがとうございます。
そうですね。。。正直、ネットでの個人の発言は「何かあった時に、その人が責任をとってくれるのか」で判断したらよいと思います。
私もコラムで様々なことを記載していますが、コラムに関する相談が来た時には、一人ひとりちゃんと対応しています。
亜鉛に関しては、サプリでとっていて過剰症になっている方も見かけるので、短期的に摂取するのはよいですが、モニタリングしないまま
漫然と投与を続けるのは好ましくないですね。