- 手足の先がいつも冷たくて爪も割れやすい
- 上半身は温かいのに下半身が冷えやすい
- いつも厚手の服を着ているのに寒く感じる
という方はいませんか?冬に来る「冷え性(冷え症)」、とても辛いですよね。冷え性も「自分の体質」だと思ってあきらめてしまっている方も多いようです。実際「西洋薬で冷え性に効く薬」というのもなかなかなく、クリニックや病院でも難渋しやすい疾患として挙げられます。
その中で一日の長があるのが「漢方薬」。古くから漢方の世界では冷え性を病気の1種ととらえ、さまざまな漢方薬が冷え性に対して活用されているのです。
では、どういった漢方薬が冷え性に効果的なのでしょうか?「手足の冷え」「全身の冷え」「下半身冷え」など冷え性のタイプにあわせた漢方薬とその効果について解説していきます。
Table of Contents
冷え性に使う漢方薬とは?

そもそも「冷え性」とはどういう状態のことを指すのでしょう。
冷え性を広辞苑で調べると「冷えやすい体質。血液の循環のよくない身体。特に足・腰などの冷える体質」と記載されています。英語では「Cold Sensitivity」「Cold Intolerance」で表現されますね。
日本の疫学調査では「日本人女性の2人に1人、男性も3割が冷え性を感じている」というくらい、冷え性を自覚する方が多いのですが、西洋医学ではまだ十分に解明が進んでおらず、西洋薬で特異的な薬があるわけではありません。
一方、東洋医学・漢方薬の世界では「冷え性」に対して古くから研究が行われ、さまざまな薬が冷え性に対して応用されています。実際
- 全体が冷えるタイプ(全身型)
- 手足が冷えるタイプ(四肢末端型)
- 下半身が冷えるタイプ(下半身型)
- 冷えていると感じてしまうタイプ(体感異常型)
- 部位別の症状に冷えが関係するタイプ(症候型)
などに分けられ、さらに個人のもともとの体質や「証」に合わせて漢方薬が処方されますね。
では、具体的にどんな漢方薬が冷え性に使われるのでしょう。今回は数ある漢方薬の中から
- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 八味地黄丸(はちみじおうがん)
について解説していきます。
(参照:What is cold intolerance? J Hand Surg Br. 1998 Feb;23(1):3-5.)
冷え性で使われる漢方薬①:当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

当帰四逆加呉茱萸生姜湯は冷え性の中の「末端冷え性」で最も使われる漢方薬の1つ。具体的には「体力がなく、手や足の先の冷え、下肢の冷えがひどい人のしもやけ、下腹部痛や腰痛、下痢、冷え症の女性の月経痛に適する」とされています。(ツムラ38番)具体的な生薬は次の通りです。
- 当帰(トウキ):よく更年期障害にも使われる漢方薬で血のめぐりを良くします。
- 桂皮(ケイヒ):ケイの樹皮や周皮の一部を除いたもの。体の冷えを取り除き、血の巡りをよくする成分が含まれています。
- 芍薬(シャクヤク):芍薬の根の皮を取り除き乾燥させたもの。シャクヤクに含まれるペオニフロリンなどの有効成分には鎮痛鎮静・筋弛緩のほか、血管拡張作用もある。
- 細辛(サイシン):ケイリンサイシンの根。健胃作用や抗アレルギー作用、鎮痛作用があります。
- 呉茱萸(ゴシュユ):ゴシュユ(ミカン科)の果実を乾燥させたもの。エボジアミンなどの作用により、体を温め、鎮痛作用をもつといわれています。
- 生姜(ショウキョウ):これはおなじみの「ショウガ」ですね。もちろん体全体の代謝を高め温める作用もありますが、胃の機能を高める「健胃作用」もあります。
- 木通(モクツウ):アケビのつるを横切りにしたもの。利尿作用や消炎作用、むくみの改善効果があるといわれています。
- 大棗(タイソウ):棗(ナツメ)を乾燥させたもの。筋肉の急な緊張をやわらげたり、神経過敏を沈める作用があるといわれています。
当帰が血行をよくして体を温め、桂皮・芍薬が気分を落ち着かせながら痛みを取り除き、生姜・呉茱萸・細辛で痛みの緩和と保温効果、大棗で神経過敏を沈め痛みを和らげるという処方になっています。簡単にいうと「保温としもやけに伴う神経痛をやわらげる効果」が中心となった配合ですね。
当帰四逆加呉茱萸生姜湯は、実際に「冷え性」に対して小規模ですが臨床試験が行われています。
実際、末端冷えをもつ58名(23-79歳)の女性に対して、ランダム化比較試験を行ったところ、四肢末端の表面温度と血流の回復値が有意に高かったというデータがあります。
ただし、当帰四逆加呉茱萸生姜湯は、数ある漢方薬の中でも非常に苦い漢方薬の1つ。あまり苦いのが苦手な方は、「当帰芍薬散」など他の漢方薬の方がよいかもしれませんね。
(参照:漢方治療エビデンスレポートより)
冷え性で使われる漢方薬②:当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
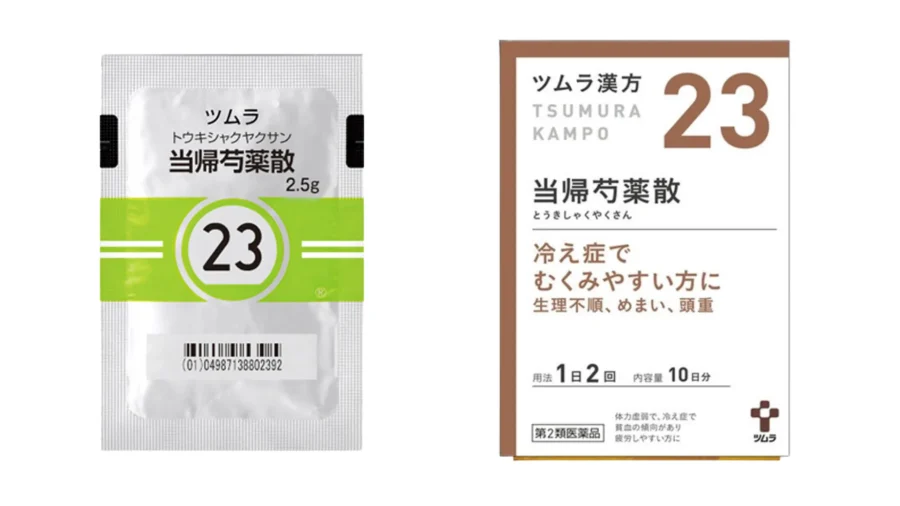
当帰芍薬散も体の芯が細い冷え性の方によく使われる漢方薬の1つ。具体的には「体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える方」によく使われます。(ツムラ23番)後述する桂枝茯苓丸や加味逍遥散と並んで「3大婦人科薬」とも言われていますね。具体的な構成される生薬は次の通りです。
- 当帰(トウキ):よく更年期障害にも使われる生薬で血の巡りを良くします。
- 川きゅう(センキュウ):血行不良を抑える生薬。血の巡りの不調に伴う精神症状を改善します。
- 芍薬(シャクヤク):芍薬の根の皮を取り除き乾燥させたもの。シャクヤクに含まれるペオニフロリンなどの有効成分には鎮痛鎮静・筋弛緩のほか、血管拡張作用もある。
- 蒼朮(ソウジュツ)または白朮(ビャクジュツ):発汗・鎮静・抗けいれん作用などを示します。
- 沢瀉(タクシャ):サジオモダカの塊茎を乾燥したもの。利尿作用があります。
- 茯苓(ブクリョウ):マツホドの菌核。動悸や筋肉のけいれんなどを抑える効果があります。
全体的にみると、当帰芍薬散は「全体の血の巡りをよくしつつ、水分の調節や冷えに伴う筋肉の緊張を取り除く作用」が中心の漢方薬といえますね。
実際、当帰芍薬散が有効である冷え性のタイプを見た論文によると、以下の特徴がある場合は当帰芍薬散が効果的であるとしています。
- 腹部の冷えが中心であるケース
- めまいを伴いやすいケース
- 目のかすみがあるケース
- のぼせがあるケース
- 怒りっぽさや耳鳴りがないケース
なので、もともと虚弱気味で上記の特徴がある場合は、当帰芍薬散を一度試してみるのもよいかもしれませんね。
(参照:当帰芍薬散および加味逍遥散が有効な冷えについての検討)
冷え性で使われる漢方薬③:人参養栄湯(にんじんようえいとう)

人参養栄湯は全身の冷え性に用いられやすい漢方薬の1つ。具体的には「体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血」に使用されます。構成される生薬は以下の12種類にも及びます。
- 人参(ニンジン):ニンジンの根。競争薬の代名詞にもなっていますね。他、協力な保温作用や消化促進作用などがあります。
- 黄耆(オウギ):オウギの根。利尿・強壮・血圧降下・末梢血管拡張などがありますね。
- 当帰(トウキ):トウキの根を乾燥させたもの。血の働きを調和し、身体のうるおいを保つ働きがあります。
- 地黄(ジオウ):ジオウの根。皮膚血流量の増加のほか、水分の調節作用や血行不良によるしびれを改善させる作用なども認められています。
- 白朮(ビャクジュツ):発汗・鎮静・抗けいれん作用などを示します。
- 茯苓(ブクリョウ):動悸や筋肉のけいれんなどを抑える効果があります。
- 芍薬(シャクヤク):芍薬の根の皮を取り除き乾燥させたもの。鎮痛効果や血行を促進する作用があります。
- 桂皮(ケイヒ):ケイの樹皮や周皮の一部を除いたもの。体の冷えを取り除き、血の巡りをよくする成分が含まれています。
- 陳皮(チンピ):いわゆる「みかんの皮」。食欲増進や体を温める作用があります。
- 遠志(オンジ):イトヒメハギの根。精神を安らかにする作用があり、物忘れの改善効果も期待できます。
- 五味子(ゴミシ):慢性の咳や喘息などへの効果が有名ですが、疲労に対しても用いられます。
- 甘草(カンゾウ):健胃・抗炎症作用などがあります。他の生薬との「調整薬」としても使われますね。
このように、滋養強壮作用のある「人参」や「黄耆」、血流をよくし鎮痛作用もある「当帰」や「地黄」、水分バランスを整える「白朮」や「茯苓」などが配合されています。
簡単にいうと人参養栄湯は「滋養強壮作用も期待しながら、『気血水』を大きく整えて冷えを改善する」ことを期待した漢方薬ですね。
皮膚科疾患における「末梢循環障害」について検討されており、23例の非常にエビデンスの低い観察研究ではありますが、31例中23例(74%)で冷え性に対する自覚症状の改善や皮膚温の改善などが認められました。
普段から栄養不良で全身が冷えやすいという方は試してみてもよいかもしれませんね。
(参照:皮膚科領域の末梢循環障害に対する人参養栄湯の有用性の検討)
冷え性で使われる漢方薬④:桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
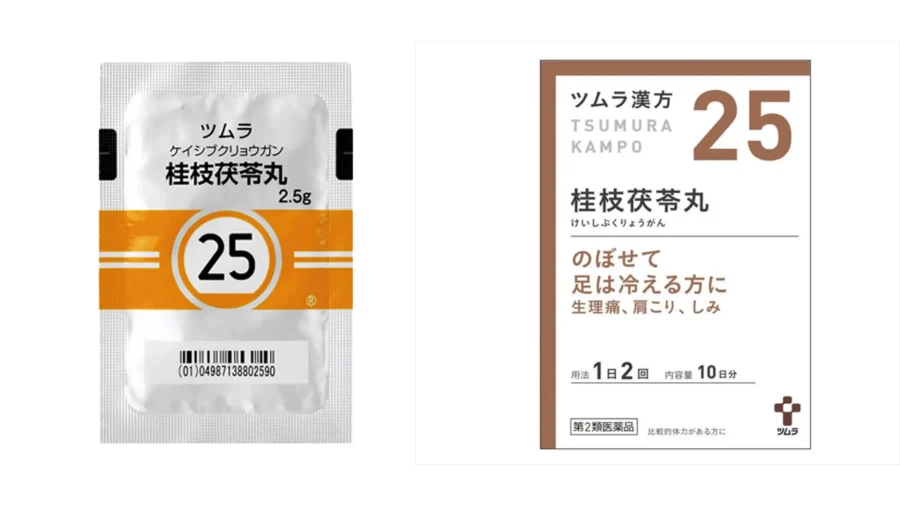
桂枝茯苓丸は特に「上半身がのぼせるのに下半身が冷えやすい方」に対する漢方薬として有効とされる漢方薬の1つ。
具体的には「比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症: 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症注)、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび」に使われます。
構成される生薬は次の通りです。
- 桂皮(ケイヒ):ケイの樹皮や周皮の一部を除いたもの。体の冷えを取り除き、血の巡りをよくする成分が含まれています。
- 芍薬(シャクヤク):芍薬の根の皮を取り除き乾燥させたもの。鎮痛効果や血行を促進する作用があります。
- 茯苓(ブクリョウ):マツホドの菌核。動悸や筋肉のけいれん、水分を整える効果があります。
- 桃仁(トウニン):モモの種。血液の流れをよくする作用があります。
- 牡丹皮(ボタンピ):牡丹の根の皮。桃仁と同様、血液の流れをよくするので、月経痛などにも使われます。
このように、かなりシンプルな構成ですよね。桂皮は頭ののぼせる症状(気逆)によく使う薬の1つ。芍薬は鎮痛作用がありながら、水分のバランスを整える「茯苓」、血液の循環をよくする「桃仁」や「牡丹皮」などで構成されています。
簡単にいうと桂枝茯苓丸は「頭ののぼせを取り除きながら、骨盤の『血のめぐり』を整え下半身冷えを防ぐ」狙いがある漢方薬といえますね。
桂枝茯苓丸は、更年期障害にもよく使われる薬の1つ。実際、桂枝茯苓丸は「ホットフラッシュの改善薬として研究が行われています。
実際の研究報告によると、基礎疾患をもたず3か月以内にホルモン補充療法をしていない352名の女性の方(46-58歳)に対して、桂枝茯苓丸かホルモン補充をランダムに内服させた試験では、桂枝茯苓丸を内服した方は足のつま先の血流が増加する傾向にあったとのことでした。
冷え性で使われる漢方薬⑤:八味地黄丸(はちみじおうがん)

八味地黄丸も冷え性には比較的用いられやすい漢方薬の1つ。具体的には「体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ」に使われます。
構成される生薬は次の通りです。
- 地黄(ジオウ):ジオウの根。皮膚血流量の増加のほか、水分の調節作用や血行不良によるしびれを改善させる作用があります。
- 山茱萸(サンシュユ):サンシュユの果肉。脾胃を温め、冷えによる疼痛や知覚麻痺などをよくする作用があります。
- 山薬(サンヤク):ヤマノイモやナガイモの根を乾燥させたもの。滋養強壮作用や抗炎症作用があります。
- 茯苓(ブクリョウ):マツホドの菌核。動悸や筋肉のけいれん、水分を整える効果があります。
- 沢瀉(タクシャ):サジオモダカの塊茎を乾燥したもの。利尿作用があります。
- 牡丹皮(ボタンピ):牡丹の根の皮。血液の流れを良くする作用があります。
- 桂皮(ケイヒ):体の冷えを取り除き、血の巡りをよくする成分が含まれています。
- 附子(ブシ):トリカブトの根。水分の代謝を盛んにして、悪寒や体の関節痛などを抑えます。
よく八味地黄丸は過活動膀胱や神経痛などにも用いられやすく、冷え性だといわゆる「腰冷えしてトイレが近い方や神経痛がひどい方」に使われますね。
実際、高齢者の冷え性の方(平均年齢62.5歳)37症例に使った報告によると、冷えの改善が見られたのは20.6%、軽度改善例が35.3%であり、全体として55%以上が改善傾向であったとしています。特に
- 手足腰の痛み:44.8%
- 手足腰の脱力感:39.3%
- 手足腰のしびれ:59.1%
- 手足腰の冷え:31.8%
に対して効果があったとしています。高齢の冷え性の方、神経痛や膀胱症状がある方にはオススメの漢方薬です。
(参照:高齢者の手足腰の痛み・脱力感・しびれ・冷えに対する八味地黄丸の効果)
冷え性の漢方薬を使用する際に注意すべき点は?

冷え性の漢方薬を使う際に注意すべき点があります。それは「冷え性の原因検索は一度きちんと行うこと」です。
漫然と冷え性に対して漢方薬だけを使用していても効果がありません。原因は全ては解明されていませんが、甲状腺機能低下症や鉄欠乏性貧血などさまざまな基礎疾患で冷え性になりやすいことが言われています。
他にも思わぬ原因で「冷え性」になっているかもしれません。いずれにせよ放置せず医療機関でも相談いただくことをオススメいたします。
こちらもあわせてオススメです
- 不眠症・睡眠障害について解説【眠れないあなたへ】
- 立ちくらみやふらつきで多い神経調節性失神・起立性低血圧について【原因・予防・治し方】
- しもやけは予防できる?しもやけ(凍瘡)の原因や対策・薬について解説
- 片頭痛【症状・診断基準・対処法・薬】について解説
- 女性の頻尿に多い過活動膀胱について【症状・検査・治療薬】
- 禁煙外来について解説【成功率・費用・副作用・保険適応】
【この記事を書いた人】
一之江ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。




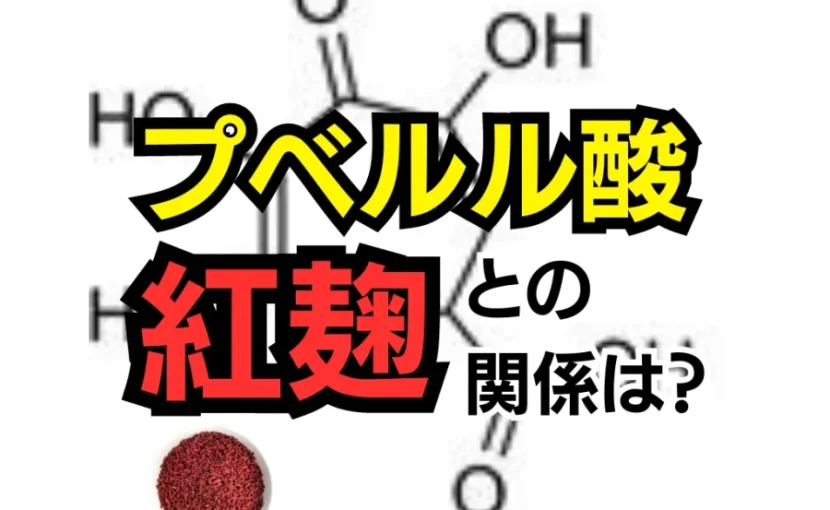

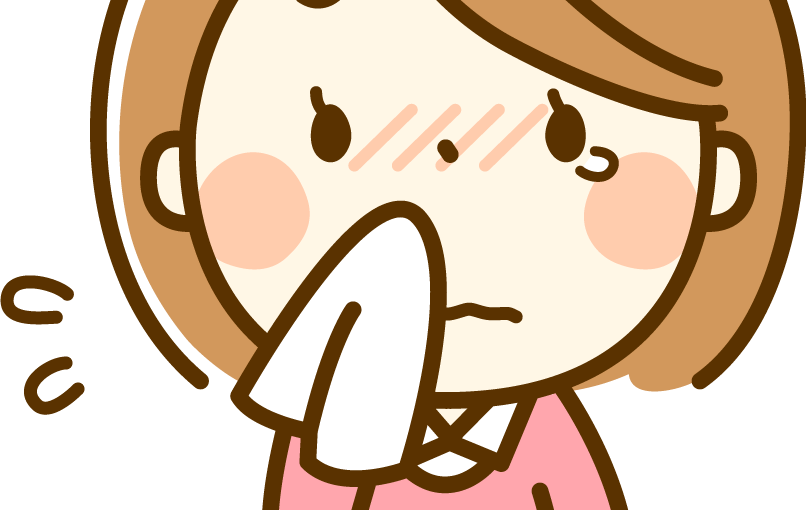











この記事へのコメントはありません。